
第2調節池 学習環境フィールド3

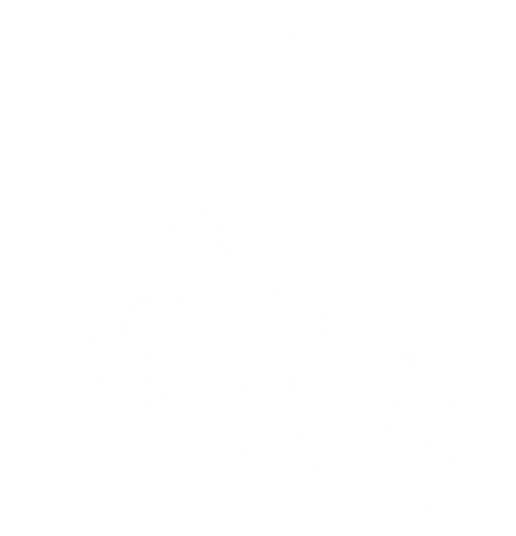

各調節池の特色

生きものや風景の四季折々の表情
第1調節池
3つの調節池の中で最も広く、ハート形の谷中湖があります。谷中村史跡保全ゾーンの周辺は遊歩道も整備され、自然観察には最適です。5月にはトネハナヤスリ、ノウルシ、アマドコロ、エキサイゼリ、ヌマアゼスゲなどの植物が見られ、梅雨の季節には、ハンゲショウやハナムグラが見頃になります。この頃には、オオヨシキリ、コヨシキリ、カッコウが盛んに鳴いています。
第1調節地の一部ではオオセッカを見ることもできます。秋にはワタラセツリフネソウが咲き誇り、史跡ゾーンの延命院跡周辺では一面のヒガンバナが見事です。冬にはたくさんのチュウヒ、ハイイロチュウヒ、ベニマシコ、オオジュリンなどの冬鳥を見ることができます。
史跡ゾーンの入り口あるウォッチングタワーに上ると渡良瀬遊水地が一望でき、上空を舞う猛禽類(もうきんるい)を見ることができるかもしれません。
谷中湖には秋から冬にかけて、たくさんの水鳥が飛来します。平成26(2014)年の冬には初めてツクシガモが訪れ、それ以降も散見されています。1月中旬になると谷中湖の干し上げが始まり、潜水性のカモ類は減りますが、替わりに関東一円からコウノトリが集まってきます。
また、多くの運動場が整備され、野球やテニスなどスポーツを楽しむ環境が整っています。またスカイダイビングやサイクリングも楽しめます。
第3調節池
北部に位置する第3調節池は3つのうちで一番小さな調節池です。特別な施設はありませんが、静かで自然の景観を満喫できるエリアです。西の端には落羽松(ラクウショウ、別名ヌマスギ)の林があります。この辺りは人工物などがないことから、ヨシ焼きのときはヨシが燃え上がる様を間近に見ることができます。
東赤麻橋の近くの掘削跡地は水が溜まってほどよい湿地となり、カワセミやコウノトリ、またカエル類も多く見られます。
東西に走る送電線の下の道は野鳥の観察に適しており、ときには鉄塔にとまる猛禽類を見ることができます。


ヨシ焼き/©堀内洋助


コウノトリ巣立ち/©堀内洋助


コヨシキリ/©堀内洋助

第3調節池
第1調節池
第2調節池
谷中湖
第2調節池
鷹見台からは第2調節池が一望でき、文字通り猛禽類の観察に絶好の場所です。秋から冬にはチュウヒ、ハイイロチュウヒ、オオタカ、ノスリ、コチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、コミミズクなどを見ることができます。初夏には、オオヨシキリやコヨシキリの鳴き声があふれます。
鷹見台の対岸には桜堤、遠くには富士山を望み、富士山をバックに雄大なヨシ原を満喫することができます。池には浮島のようになった観察ポイントと、池の一部と桜堤を結ぶ散策路が整備されています。広い駐車場やトイレもあるので自然観察の拠点に最適です。「渡良瀬遊水地湿地保全再生基本計画」にもとづいて、治水と保全を両立させた掘削が行われています。これまでに環境学習フィールド1・2・3・4、水位変動型実験地、湿潤環境形成実験地、大型鳥類休息実験地などが掘削されています。
掘削後は、市民や地元自治体が中心となって湿地のメンテナンスが行われ、タコノアシ、ジョウロウスゲやミゾコウジュなどの絶滅危惧種が埋土種子から復活してきています。環境学習フィールド3では、官民協働で外来種除去作戦が行われています。
平成30(2018)年にコウノトリの人工巣塔を設置したところ、令和2(2020)年に野外絶滅後東日本初となるコウノトリの野外繁殖が実現しました。それ以降毎年コウノトリが繁殖しています。現在は、渡良瀬遊水地内に合計3つの人工巣塔が設置されています。


ワタラセツリフネソウ/©堀内洋助
-k_JPG.jpg)
落羽松
(ラクウショウ:ヌマスギ)
-k_JPG.jpg)
環境学習フィールド[3]

ウォッチングタワー


校威を背負って/©塩田敏�夫


熱気球とカモ/©堀内洋助

